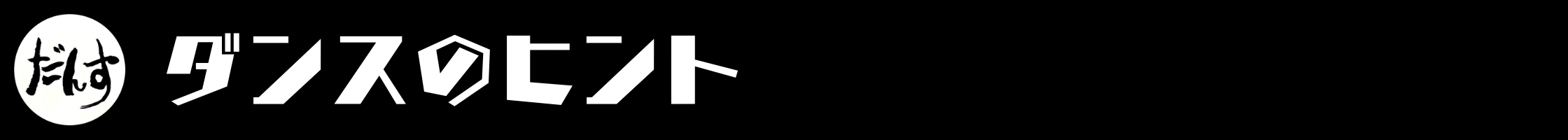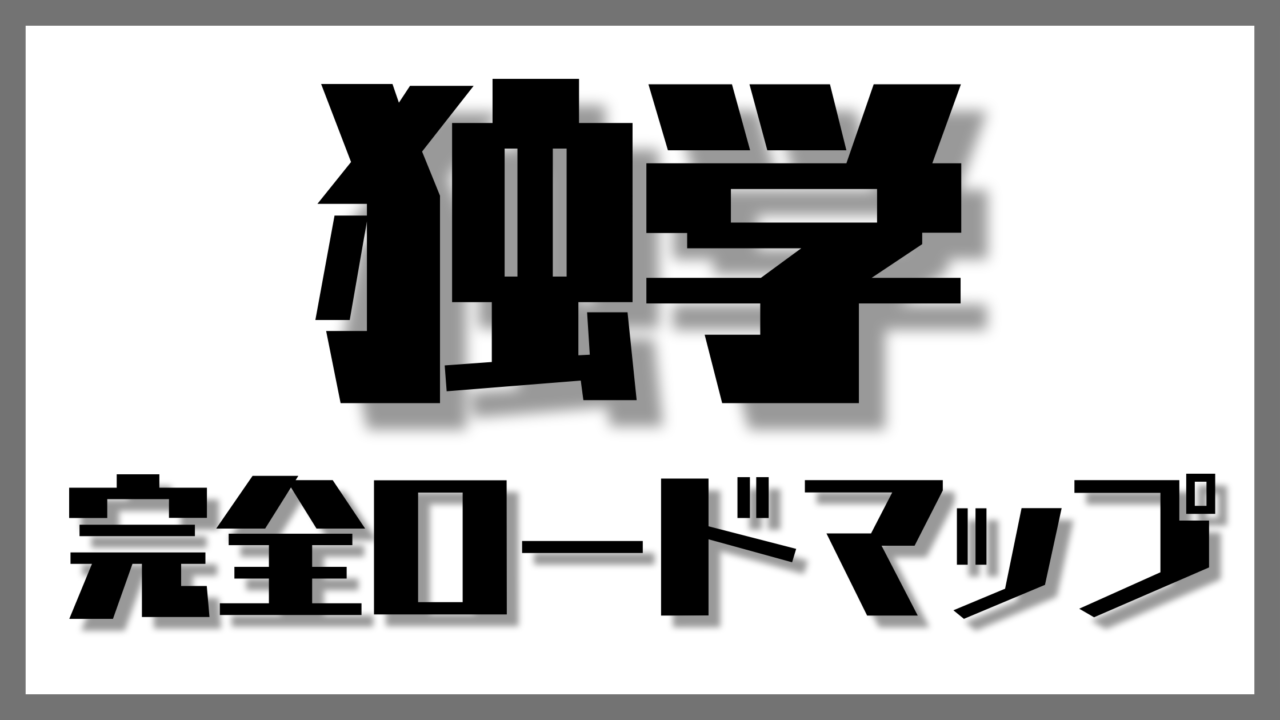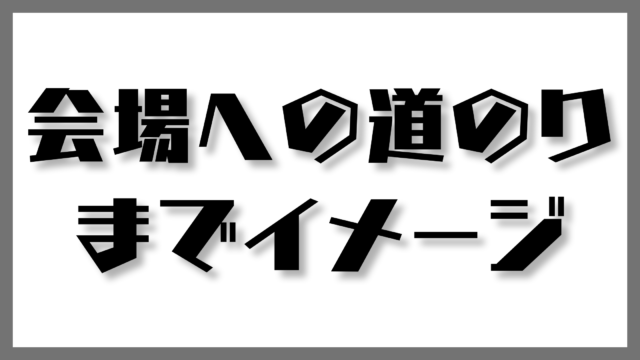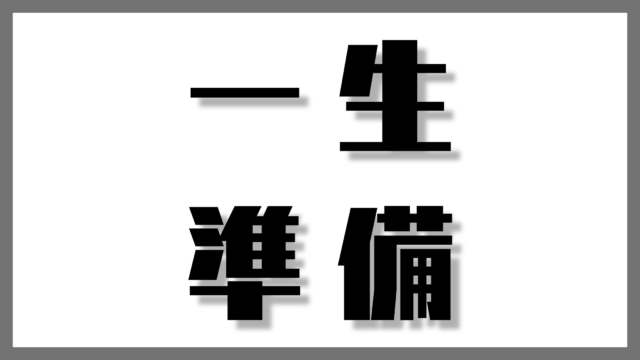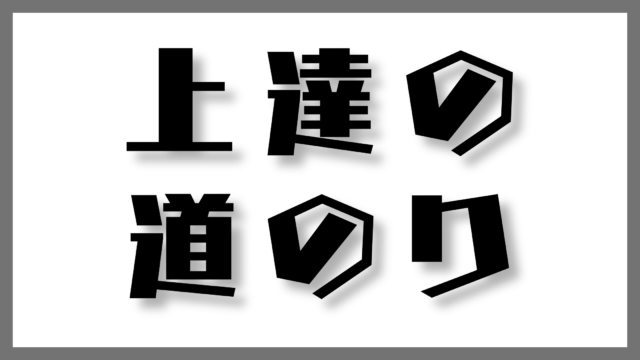この記事は、ダンス初心者
(特にストリートダンス系をメインにしたい人)
が「独学」でスタートして、まずは
「ちょっと踊ってみてよ!」と言われたときに即興でもある程度踊れる
ようになるための、実践的な上達方法を示したものである。
独学でダンスを始める時の、
・よくある悩み
・ハマりがちな落とし穴
・そうならないための具体的な注意点
も記載している。
1つの技を教えてくれるショート動画はたくさんあっても、
この記事のように、全体としてダンスがどのように上手くなっていくのか
を解説した記事はあまりみたことがないのではないだろうか?
ダンスを独学で始めるための10ステップ:完全保存版

〜初心者から「ちょっと踊ってみてよ!」と振られたときにすぐ踊れるくらいのレベルに〜
ダンスをいざ始めたいと思ったときに感じるのは
①まずどう始めて
②どうやって上手くなって
③どう練習を継続していくんだろう
という疑問なはず。
(むしろ、疑問すらなくて、とにかく始めるためにどうすればいいのか何もわからないという人もいるかも)
わざわざその人にあったやり方を個別指導してくれる先生はいないし、
「独学」
では、特にその迷いが大きい。
SNS等で一つの技のやり方のレクチャーショート動画を見つけても、
「その後、どう他の技とつなげて上達していけばいいのか」
がわからなければ、せっかく高まったやる気はまた下がり、
徐々にダンスから遠ざかってしまう事が多い…

なので逆に、
「初心者のほとんどが、大体の場合こうやって上手くなっていく」
という道筋がある程度示されていれば、モチベーションがグッと高まる。
このアカウントではこれまで
「独学はキケン」
という立場で発信してきた。
しかし、それでも
「まずは部屋でこっそり練習したい…」
「スタジオに行けるレベルになるための練習をしておきたい…」
という声を多くいただいた。
なので今回、
もし本気で「独学ダンス」を始めるならどういう道のりで練習すればいいのか、10ステップに全てを書き残した。
自分の現在地に合わせて何度でも読み返しできるよう体系的に整理してあるので、是非ブックマークしておいてほしい。
(また、内容はしっかり定期的に更新していく)
まずは全体をざっくりと読んで、
「上手くなるまでは、大体こんな流れで進んでいくんだな」
と全体像を頭に入れるのがオススメ。
現在地がわかっている方がやる気も出やすい!
また、文字だけではわかりづらいので、
独学でダンスをするのに役立つ動画
もたくさん紹介していく。
それでは、早速ステップ1から順番にご紹介。

ステップ1. 「どんな踊りをどこで披露したいのか?」をイメージ
早く踊るための練習法を教えろ…
と思った方も、
少しだけ待ってほしい。

なぜなら、
もし
「とりあえずあの有名な振り付けを完コピしてみたい」
という目標なら、YouTubeのダンスカバー動画を参考にするのが近道かもしれない。
でも、
「数年後に有名なコンテストで結果を出したい」
とか、
「先に始めたあの友人より絶対に上手くなりたい」
という目標なら、
確実なスキルアップが必要になるので、
振り付けを始める前にがっつり基礎を固める必要があるかもしれない。
このように、
「ゴール設定」
によって、進むべき道順や目指すレベルはガラッと変わる。
(つまり、このあと紹介する残りの9ステップのどこに比重を置くかが変わってくる)
また、この設定をする時は
「想像するだけでワクワクするような自分の踊る場面」
をハッキリ決めるのが大事。

例えば、
ダンスの練習をしていることを知らない友人たちに、
結婚式などのイベント(もしくはSNS)でいきなり踊りを披露して、
みんなを驚かせたい…!
…など。
「なんとなく踊りたい」だけだと、目指す踊りから逆算して、今自分がやるべきことを具体的にイメージできないので、
気付いたらいつの間にかモチベーション自体が消え去っていた…
なんてことになりやすい。
例えば、
「自分のダンスのショート動画をアップするだけ」なら、
お手本の動画をスローで再生して何度も真似してみることになる。
しかしそうではなく、
一曲しっかりと振り付けを覚えたいなら、
まず
・その中で使われているダンスジャンルがなんなのか
・どういった基本技を習得する必要があるのか
などを、調べないといけない。

ステップ2. ジャンルを見極める:どれをメインに練習するか決める
自分が踊りたいと思うきっかけになったダンサーは誰? その人のスタイル・ジャンルは?
練習を始めるには、自分のダンスのジャンル・スタイルをある程度絞る必要がある。
例えば、HIPHOP、POP、LOCK、HOUSEなどのように、漠然と「ダンス」というよりももう少し具体的に「〜ダンス」とそのジャンルを明確にしておく。
そうすることで、
「〜のジャンルの誰々というダンサーみたいになりたい」
と、目標を定めてから的確に情報収集していくことができる。
以下に、代表的なダンスのジャンルを紹介しておく。
やりたいジャンルが決まっている人も決まっていない人も、
・どんな成り立ちのダンスがあるのか
・他の多くのジャンルに応用できるのはどのジャンルなのか
・第一印象で自分が一番やりたいと思えるジャンルはどれか
を調べるための参考にしてほしい。
※以下に掲載しているジャンルごとの動画は、
すべて見所の部分から「途中再生」されるように設定されている

1:ヒップホップ(HIPHOP):迷ったらやっとけ!汎用性高し
ヒップホップダンスは、1970年代にアメリカニューヨークで生まれたスタイル。
大きな特徴は、
音楽のビートを明確に捉え、身体全体で自由に音楽を表現するところ。
必要なリズム感やステップの範囲が広く、どんな場面でも使える踊り。
初心者にとって最もとっつきやすく、「将来的にも役立つ」ジャンルといえる。
基本的なベースのテクニックとしては、
ダウンのリズム(膝を軽く曲げながら音に合わせて上下に揺れる動き)や、
アップのリズム(つま先やかかとで軽く弾むように上へリズムを取る動き)などがある。
それらの基本的なノリの型が存在し、それを覚えれば「自分なりにアレンジして踊れる点」が魅力。
(最初は、歩きながらそれをやるだけでも難しい)
また、ヒップホップは
「自分を自由に表現する」
ことが重視される。
そのため、HIPHOPのジャンルであっても踊り手によってまったく異なるスタイルが生まれる。
また、使われる曲も幅広い。
HIPHOPはもちろん、R&Bやファンク、最近のポップスやエレクトロ調の曲でも対応しやすい。
代表的なステップとしては「ツーステップ」や「ランニングマン」、「ハッピーフィート」などがよく取り入れられる。
これらを組み合わせるだけでも、
初心者が十分楽しめるダンスが完成する。
(それぞれの動きは後で動画で紹介!)
加えて、ヒップホップでは基礎練習として
・アイソレーション(身体のパーツを個々に分けて動かす練習)
・リズムトレーニング
の練習が丁寧に行われる場合が多いため(できないと踊れないため)、
「ダンス全般で必要な身体操作の基礎が自然に身につく」
のもメリット。
初心者がダンスを始める際に、
「まずは音楽に乗る楽しさとステップの基礎を一通り学びたい」
と考えるなら、ヒップホップほど適したジャンルはない。
何より、ヒップホップはその成り立ち的にも、
他の様々なジャンルを取り込みながら成立してきたジャンルの踊りである。
そのため、ここで得た経験やリズム感は、
後にどのダンスへ進んでも
大いに活かすことができる。
「汎用性」と「自由さ」を両立する選択肢がヒップホップなのである。
2:ロッキング(Locking):割とすぐにかっこよく踊れる
ロッキングは、ファンキーな音楽(ディスコっぽい音楽というとイメージしやすい)に合わせて、
腕や上半身の動きを大きく使い、コミカルかつエンターテインメント性の高い表現をするのが特徴。
最大の見どころはもちろん
「ロック(Lock)」
と呼ばれる動作。
腕や体を素早く動かしたあとに、
強めのビートに合わせて「ガチっ!」と動作を止めるもの。
音楽に合わせてガチっと止まることで、観客に強いインパクトを与えられる。
また、基本的に「楽しく笑顔で」踊られることが多いジャンルでもある。
「ロック」や「ポイント(指差し)」などの分かりやすい技でメリハリがあり、
見ている側のテンションが上がりやすい。
初心者が取り組む場合、「リズムの取りやすさ」と「止めるタイミング」のインパクトがわかりやすく表現できるため、
基礎さえしっかり押さえれば、他のジャンルと比べて早めにかっこよく踊ることが可能。
基本の技としては「ポイント(指差し)」「トゥエル」「ロック」「スクービードゥ」などがある。
それらをタイミングよく組み合わせることでロッキングらしさを出すことが可能。
ベースのリズム感だけでなく、それらの基本技によって、
・一瞬の静止
・ジャンプ
・着地
・ポイント
ような動きのメリハリが多数あり、観てる側を飽きさせない。
ある程度の型が決まっているため、初心者が入りやすいジャンルである。
3:ハウス(House):軽やかなステップで足さばきを見せつける
ハウスダンスは、4つ打ちのハウスミュージックに合わせてステップを刻むスタイルが特徴。
(ズッ、パン、ズッ、パン、ではなく、ドッ、ドッ、ドッ、ドッという一定のリズム)
特に「フットワーク(足さばき)」と「ジャッキング(腰を上下にうねるように動かす基本動作)」が重要視され、
アップテンポの曲に合わせて足を軽快に動かすスタイルが魅力。
リズムを捉えながら足元でステップを繰り返し、細かな音を足の色々な部分を使って表現する。
曲と一体になりやすいため、心地よく長時間踊れてしまう。
初心者にとっては、足だけでなく「上半身の独特なノリ」も覚える必要があり、
最初は難しく感じる可能性が有る。
しかし、一度ゆっくりとベーシックステップを繰り返し練習し、慣れてきたら音の速さを上げるという段階を踏めば、自然とビートと一体化する感覚を得やすい。
ハウスダンスはヒップホップのように身体全体を大きく使うというよりも、
細かいステップワークに重きを置くため、
少しクールで、大人の渋さやセクシーさのあるジャンル
であると言える。
また、ドン、ドンというビートに合わせて力強くステップを踏んだり、
あえて「ちょん、ちょん」と優しく音を取ったりと、
足での音どりの表現力が大幅に高まる。
他ジャンルへの応用という点では、ジャッキング(腰を上下にうねるように動かす基本動作)によって体幹を使う時間も多いので、軸の安定感やリズム感が磨かれやすい。
ハウスを習得しておくことで、他のダンスを踊る時にも自然にテクニカルなステップを入れ込む事ができ、玄人感を高める事ができる。
4:ジャズ(Jazz):バレエが基礎!身体のラインやメリハリが美しい
ジャズダンスは、ブロードウェイやミュージカルなどで広く取り入れられてきた、
舞台映えする優雅なスタイル。
ディズニーランドなどで踊るダンサーのようないわゆる「テーマパークダンサー」に最も求められるのがこのジャンル。
(ショーにおいて、身体のラインの美しさや動きのダイナミックさ、強弱のメリハリが求められるため)
そのルーツはアフリカ系アメリカ人のリズムダンスにあり、
そこにバレエやモダンダンスの要素が融合することで多彩な動きや表現が可能になっている。
大きな特徴は、身体のラインの美しさやダイナミックな動きを重視する点。
例えば、
・ターン
・キック
・ジャンプ
といった華やかなテクニックが含まれる。
しなやかで優雅なイメージを持たれやすいが、一方で力強い表現も多く、ドラマチックな振付をする振付師もいる。
初心者にとっては、バレエの基礎に近い
・ストレッチ
・アイソレーション
・重心の移動
などを一から学ぶことができるため、
正しい姿勢や体幹の使い方を身につけられる。
また、綺麗なシルエットが重視されることから、
柔軟性の向上
にもつながる。
足先や指先など細部まで意識を向けながら動くため、
身体操作の理解が深まるのもメリット。
(ちょっとした指の角度やつま先の置き方など、繊細で美しい表現が多い)
また、ジャズダンスは幅広い音楽に合わせられるため、自分の好きな曲に振り付けを付けることもしやすい。
さらに、表現力を高める練習として、振付の中で感情やストーリーを表現する場面もある。
こうした「演劇的要素」が含まれることで、
ダンス全般に活かせる演出力やアピール力も身につく。
身体構造からシルエットをイメージして、ダンスの基礎をしっかり築きつつ、
「ステージでも映える技術」を学びたい初心者にとっては、ジャズダンスから始めるのもいい選択かもしれない。
5:ポッピング(Popping):「ロボットダンス?」「ムーンウォーク?」
ポッピングは、
筋肉に瞬間的に力を入れて生み出す「ポップ」(ヒット)
という動作が最大の特徴である。
腕や脚、肩、胸など、身体の各パーツの筋肉を
「ビートに合わせて収縮させる(振動させる)」
ことで瞬間的に体全体を「ドンッ!」地震のように震わせ、視覚的にインパクトを与える。
さらにウェーブ(波のように関節を連動させる動き)や、
ストロボ(点滅するように断続的に動く技術)、
ロボットなど、
目の錯覚を利用したエフェクト的な表現も多用されるため、
・他ジャンルよりも大きな可動域でのアイソレ
・ヒットやウェーブのような特殊な筋肉や関節の使い方
・急に一時停止したかのような急激なストップ
が必要になる。
マイケルジャクソンのムーンウォークもこのpoppinというジャンルに含まれる!
初心者が最初に苦労しがちなのは、どう筋肉を弾けばよいのか、
筋肉の使い方の感覚を掴むこと。
これができないとポップ(筋肉を弾く)ができない。
つまり、踊ることができない…。
そう、poppinは不思議な動きがすごく魅力的な一方で、
踊れるようになるまでに時間がかかってしまうのである。
しかし、短い振動のようなヒットの感覚を繰り返し練習することで、
少しずつ身体の各部位のコントロール能力が向上する。
ドラムのビートから他の楽器、さらには歌声までも、ポップやウェーブ等を使って表現できてしまうのがpoppinの醍醐味。
取れる音が細かいので、音楽の拍や裏拍を的確に捉えるリズム感も鍛えられ、
大小様々なビートを感じる耳が養われるのは大きなメリット。
踊れるまでに苦労する分、
不思議な動きを習得した時の喜びは格別。
ポッピングはヒップホップやハウスなどとも相性がよく、
ミックススタイルで踊るダンサーも多い。
複数のジャンルを融合して「表現の幅を広げたい人」にも向いている。
見た目にわかりやすい「ロボットダンス」的な要素があり、
観客を驚かせやすいことからバトルやショーなどの場で目立ちやすいジャンルでもある。
不思議な動きで観てる人を驚かせたい、全身を細かく使って全ての音を芸術的に表現したい、
という人におすすめのジャンル。
6:ブレイキン(Breaking):いわゆるブレイクダンス、「くるくる回るやつ」と言われがち
ブレイキン(ブレイクダンスとも呼ばれる)は、1970年代のニューヨークで、ヒップホップ文化の一環として発展したダンスジャンル。
2024年のパリオリンピックでは正式種目になり、日本人選手の活躍が話題となった。
フロアに手や背中をついて回転したり、
高速で足を広げて動かしたりと、
アクロバティックな動き(パワームーブ)が注目されがちだが、
それだけではなく、「トップロック」や「フットワーク」などのフロアの技に入る前の軽快なステップも大きな見どころ。
・トップロック
・フットワーク
・パワームーブ(ヘッドスピン、ウィンドミルなど)
・フリーズ(曲の切れ目で動きを一瞬止めてポーズを決める技)
を組み合わせ、独自のスタイルを構築していくのがブレイキンの醍醐味。
初心者がブレイキングを始める場合、
まずは「身体の柔軟性」と「筋力の強化」が重要となる。
特に、腕や肩、腹筋・背筋を使うため、
最初は筋トレやストレッチをこまめに行う必要がある。
(一番怪我やアザが出来る可能性が高いジャンルともいえる…!)
トップロック(立った状態でリズムを取りながらステップを踏む動き)やフットワーク(四つん這いの姿勢で足を素早く動かす基礎)を覚えていく過程で、
リズム感と下半身の素早さが同時に養われる。
また、ブレイキンは元々ギャングの抗争が起源となっているため、バトル文化が盛んなことも特徴。
サイファー(輪になって順番に踊る)で即興的に技を繰り出して競い合う場面も多い。
そうした競技性がモチベーションとなり、練習を続けると高い達成感を得られるのが大きな魅力である。
派手な動きが目立つ反面、他のストリートダンスよりも怪我のリスクが高いので、無理をせず段階的に技を習得することが大事。
「今どこまでできているのか」
「できないのはどこからなのか」
を常に考えて、
失敗があればその直前に戻って土台を組み立て直すという努力
が必要不可欠。
体力、筋力とアクロバティックな要素が必要だが、うまく技が決まったときの達成感は格別であり、初心者でもコツコツ積み上げていけば必ず成長を実感できる。
男子が一度は必ず憧れるジャンル。
7:ワック(Waacking):振り回す腕が特徴的!優雅でセクシー
ワック(Waacking)は、1970年代のロサンゼルスで生まれたダンスジャンル。
ディスコミュージックに合わせてダイナミックな腕の動きとポージングを特徴的に操るスタイルである。
「ワック」という名称は、腕をしなやかに振り回してビートに乗せる動作から来ているともいわれる。
大きく腕を回したり、小刻みに肩や肘を動かしたりして、華麗かつセクシーに表現する点が最大の魅力。
さらに、自信に満ちた表情やポーズも特徴的で、それらが音楽の拍にピッタリとハマると、観客が一気に沸き立つことが多い。
初心者にはやや難しく感じるかもしれないが、
腕や肩のアイソレーション(部位ごとに独立させて動かすテクニック)を習得する良い機会になる。
また、その振り回した腕に目がいきがちだが、
ワック特有の洗練されたポージングを出すためには
腰や胸
も多く使う必要があるため、全身の各部位の連動性を気にしながら練習する。
使われる音楽はディスコやファンク、ハウスなどのアップテンポなものに合わせることが多く、音楽自体がノリやすいため、身体を動かす喜びを直感的に味わえるのもポイント。
自然にテンションが上がるのはダンスの醍醐味。
ワックは女性的なイメージが強いが、実際には男性が踊っても力強さと華やかさを表現することができる。
バトルシーンにおいては、曲に合わせて即興でアームコンボを見せ合うケースもあり、見た目のインパクトが大きいため盛り上がりやすい。
自信に満ちた表情でクールかつ堂々、激しく踊りたい人におすすめのジャンル。
ステップ3. 「柔軟性」と「アイソレーション」で体の土台を作る
「ジャンル選びも済んだことだし、いよいよ踊れる!」「振り付けを早く覚えたい」「派手な技をやってみたい」と、先に進みたくなる気持ちは痛いほどわかる。
ただ、“しなやかに”踊れるようになるには、ダンスの基礎中の基礎である、
柔軟性とアイソレーションの練習が欠かせない。
これが出来ないと絶対に踊り始めてはいけない!というものではないが、
必ず並行して取り組む必要がある。
柔軟性、アイソレーションが大切な理由
ダンスの動きには「日常では絶対やらない体の動かし方」が多数含まれている。
例えば、
・脚を高く上げたり
・胸を斜め後ろにしまい込むように動かしたり
・肩だけ前に突き出したり
といった動き。
体が硬い状態だとこれらの動きがスムーズに出せず、ぎこちなく見えてしまう。
そのぎこちなさが「素人っぽさ」や「下手さ」といった印象に繋がってしまう。
全身ストレッチ
脚、腰、背中、お腹、首まわりを重点的にほぐす。
立って前屈や開脚をしたり、座ってゆっくり上半身をひねったりして、
体の可動域を徐々に広げるのが重要。
毎回の練習前に軽くストレッチを入れるだけでも、ケガ予防と動きの質向上に効果的である。
アイソレーションの具体練習「独立した動き」を習得する
アイソレーション(Isolation)とは「分離」という意味。
首だけ、肩だけ、胸だけ…といったように「特定の部位だけを動かす練習」を行う。
これをしっかり身につけることで、
例えば音楽の中の「ドンッ」というアクセントに合わせて
・胸を一瞬で止めたり
・肩や首だけでリズムを刻んだり
と、観る人に
「そこでアクセント取るんだ…!」
と驚かれる動きが出せるようになる。
首、肩、胸、腰…などパーツごとに動かす
鏡の前で、首を左右上下にゆっくり動かす。
肩を片方ずつ前後に動かす。
胸を前後左右、右回り左回りにスライドさせる。
最初は隣の部位が一緒に動いてしまいがちだが、ゆっくり正確にやるほど「思い通りに動かせる感覚」がつかめる。
焦って速い動きにすると雑になりがちなので、最初はとにかくゆっくり丁寧に行う。
ステップ3:まとめ
柔軟性とアイソレーションは、いわば
「体をダンス仕様にアップグレードする作業」
これを疎かにすると、後の振り付け練習やフリースタイルで結局「なんかダサい…」と感じる原因になりかねない。
じっくり時間を取って取り組むべき。
ステップ4. 色々な音楽のリズムを体に取り込む
ダンスは
「音楽と一体になる芸術」
そのため、ただ派手な
ダンスっぽい動き
だけができても、音楽と合っていなければ、
ダンスとしての評価はゼロ。
「流れている音楽で楽しくなって踊る」
のがダンスなので、
動きが先行して音楽とずれる
のは、ダンスとしては全く評価されない。
音楽と動きがズレないようにするために、どんな曲でも瞬時にその曲に合わせたリズムが取れるようにする。
まずは身体が様々な曲のリズムを一瞬で捉えられるようにリズムトレーニングをしておくのが大事。
▼ここから有料は記事になります。
あなたのダンスのヒントになる動画を大量にご用意しています!
※レッスン相場が大体3000円程度なので、「レッスン前に自宅で学んでおきたい…!」という方、是非!
※1分で支払い手続きは完了します